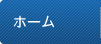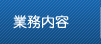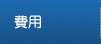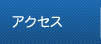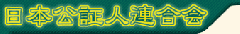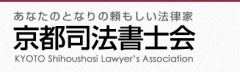HOME > 国際法務(International Legal Services)
国際法務(International Legal Services)
相続人のうち在外邦人がいる場合

遺産分割協議の際、相続人の中に海外在住の日本人が含まれるケースが最近増えてきております。
この場合、日本の不動産登記手続きに必要となる遺産分割協議書(私文書)を認証機関である現地日本国大使館等に持参し、権原ある人の面前で署名する必要があります。
印鑑登録制度のない外国に居住する日本人の場合、印鑑証明書を添付する代わりに署名証明書(遺産分割協議書への「貼付型」が望ましいです)を必要とします。
また、署名証明書と一緒に、在留証明書も取得していただきます。
相続人のうち外国籍に帰化した相続人がいる場合

近年、国際結婚の増加とともに帰化される方も増えてきております。
遺産分割協議書(宣誓供述書/Affidavit)については、現地公証人(Notary Public)等による認証を受け、公文書とする必要があります。
現地公証人事務所へ持参する遺産分割協議書等の文書は、現地公証人が理解できる言語で作成することが必要です。
当事務所では、日英での文書作成が本職において対応可能です。
遺言書の作成・通事
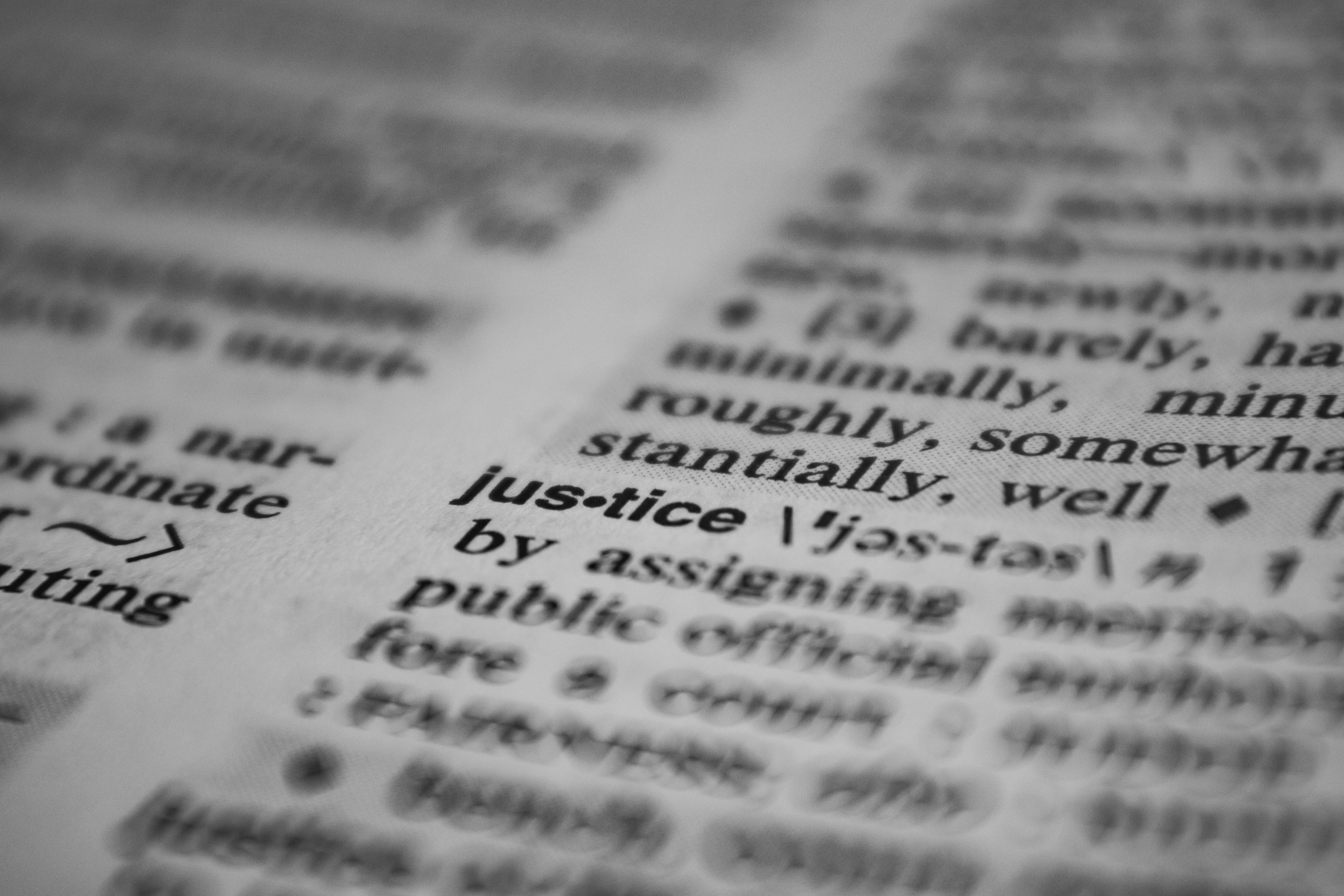
日本国籍を取得された元外国籍の方の中で、日本で遺言書を作成することを検討されていらっしゃる方も少なからずおられます。
この場合、公証役場にて作成される公正証書遺言で遺すことをお勧めしております。
本国法主義(法の適用に関する通則法36条)を採用している日本では、被相続人が日本国籍を有していれば、日本の法律が適用されます。
そうであっても、難解な法律用語を日本語で理解できる自信がない元外国籍の方も多数いらっしゃることから、公証役場では「通事(通訳)」を利用することができます。
公証役場での日英通事(通訳)のほか、遺言書の日英翻訳も本職にて対応可能でございます。